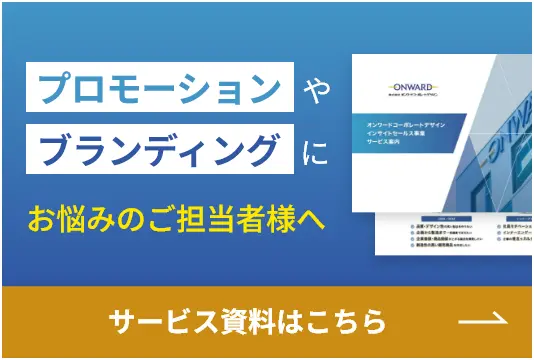目次
本記事とあわせて読みたい資料
顧客体験の進化を「体験設計」の視点から捉え直すための、実践的なホワイトペーパーを公開中です。「セールスプロモーションを軸とした顧客体験の具体化」に焦点を当てた内容になっております。
顧客接点をどう設計し、ブランド体験としてどう形にするか、そのヒントをお探しの方におすすめです。
⇒今すぐダウンロードする
なぜ今CXが注目されているのか
 スマートフォンやSaaSの普及により、顧客が商品やサービスを比較・選択することはかつてなく容易になりました。このような環境では、製品や価格そのものではなく、“どんな体験を通じてそれが提供されるか”が、ブランド選定の決め手となっています。企業にとって、顧客体験(CX)の質は競争力の重要な要素となりつつあります。
スマートフォンやSaaSの普及により、顧客が商品やサービスを比較・選択することはかつてなく容易になりました。このような環境では、製品や価格そのものではなく、“どんな体験を通じてそれが提供されるか”が、ブランド選定の決め手となっています。企業にとって、顧客体験(CX)の質は競争力の重要な要素となりつつあります。
こうした背景を受け、CXの重要性は多くの企業で認識され始めていますが、実際の取り組みはまだ限定的です。IPA『企業IT動向調査報告書2023』によれば、“顧客接点”に関してすでにDXに取り組んでいる日本企業は18.3%、PoC段階を含めても31.1%にとどまっています。
特に日本では、CXを全社横断で捉える視点がまだ十分に浸透しておらず、グローバル企業との差も広がりつつあります。部門単位での対応にとどまり、顧客接点が断片化しているケースも少なくありません。
今後は、単なる製品機能や価格の差別化ではなく、企業が一貫して“どんな体験”を提供できるかが、競争力のカギとなるでしょう。
出典:IPA「企業IT動向調査報告書2023」
UXとカスタマージャーニーの重要性

CXを構成する要素の中でも、特に密接に関係しているのが“UX”と“カスタマージャーニー”です。
UXは、Webサイトやアプリといったオンライン接点だけでなく、店舗やカスタマーサポートなどを含む、あらゆる顧客接点での使いやすさや心地よさを指し、ユーザーの印象や行動に直接影響します。一方、カスタマージャーニーは、顧客が課題に気づき、比較・検討し、購入・継続利用に至るまでの一連の体験プロセスです。
これらが十分に設計されていない場合、以下のような『体験の分断』が生じやすくなります。
・Web広告やSNSからの来店導線に一貫性がなく、店舗での体験にうまくつながらない
・ブランドメッセージと実際のサービス内容に乖離があり、信頼を損なう
・オンライン広告から遷移したページが期待と異なり、CVRが著しく低下する
こうした問題の根本には、顧客視点を欠いたUX・ジャーニー設計の課題が潜んでいます。
成功企業の取り組み:体験設計で成果を上げた事例
ここでは、体験設計を見直すことで成果を上げた3つの企業事例をご紹介します。
年間イベントの定番化を促進した体験型ノベルティ施策
ある大規模商業施設では、毎年恒例となっている大型セールにおいて、顧客の期待感や来店動機を強化するために、体験性の高いノベルティ施策を実施しました。
販促用に配布するバッグには、外観デザインだけでなく、手触り・ディテール・刺繍・タグなどにもこだわり、「そのイベントならではの特別感」を演出。結果的に、「この時期といえばこの企画」と想起されるブランディングにもつながりました。
ファッションとコスメを融合した業種横断型キャンペーン
美容業界のある企業では、コロナ禍での店頭集客減少という課題に直面し、異業種であるファッションブランドとのコラボレーション企画を展開しました。単にアイテムのデザインだけでなく、キャンペーンのキービジュアルもファッションブランドチームで制作し、統一感のあるキャンペーンを演出。顧客体験全体に統一感を生み出しました。
さらに、製品の割引優待を同梱することで、単なる“話題づくり”ではない実利的ベネフィットの提供にも成功しており、来店促進と販売促進も両立した設計となっています。
使用済資材を活用したアップサイクル施策
航空業の企業では、廃棄予定だった高品質な素材を再利用し、オリジナルグッズとして再設計するアップサイクル施策を展開。航空機の内装材などを活用し、ルームシューズなどに生まれ変わらせることで、社会課題解決への姿勢を明確に示しました。
素材や背景ストーリーも合わせて発信することで、共感を呼ぶコミュニケーション設計が実現されています。
いずれの企業も、UXを単なる表層的な見た目や利便性の向上ではなく、「顧客にどう記憶され、どう感じられるか」という体験全体の設計として捉え、世界観や文脈、ストーリー性を一貫して構築しています。
結果として、イベントの定番化やSNSでの話題化、ブランドへの共感形成といった成果につながっています。
顧客体験を高める設計プロセスと成功事例をまとめたホワイトペーパーを無料公開中!
⇒今すぐダウンロードする
顧客体験を設計する4ステップ

顧客体験を設計・改善する基本プロセスは以下の4ステップです。
ステップ1:現状分析(ユーザー調査・データ収集)
NPS調査やアクセス解析、顧客インタビューを通じて、ユーザーの行動や感情を可視化し、ペインポイント(不満やストレス)を特定します。
ステップ2:カスタマージャーニーの可視化
認知から検討、購入、再利用に至るまでの体験をフェーズごとに整理。感情の起伏や機会損失が生じているポイントをマッピングし、改善点を明確にします。
ステップ3:UX改善施策の設計
顧客接点での伝え方や情報の見せ方、チャネル間の連携方法を見直し、体験の流れを整理・設計します。必要に応じて、仮説を形にしながら具体的な設計検証を進めていきます。
ステップ4:実装・検証・改善
施策を実装後は、仮説検証や効果の可視化を通じて改善を図ることが重要です。PDCAを回し、継続的に体験をアップデートします。
顧客体験改善がマーケティングROIを高める
CX向上は単なる「満足度の追求」にとどまらず、マーケティングROIの向上にも直結します。良質な体験は継続利用やアップセルを促進し、結果としてLTVを高めます。
CX重視の企業では、好意的な言及がSNS上で増え、自然な紹介へと繋がるため、広告に頼らずとも新規顧客を獲得しやすくなり、CPAの削減も期待できます。
よくある失敗パターンとその回避策
CX改善に取り組む企業は増えていますが、実際には「期待していた成果が出なかった」「途中で頓挫してしまった」といったケースも少なくありません。その多くは、施策が表層的であり、CXの本質的な設計にまで踏み込んでいないことに起因します。
主な失敗パターンの類型と原因
1.表面的な施策に終始してしまう
「問い合わせフォームのボタン色を変えてみた」「アンケートをとったが、その後の分析やアクションがない」など、UX改善を見た目や一時的な操作性に限定してしまうケースです。顧客の行動や心理の背後にある本質的な課題を捉えずに手を打っても、根本的な改善にはつながりません。
2.定量データだけに頼ってしまう
サイトの利用状況やCVRなど、数値指標だけを頼りに判断し、顧客の感情や文脈を見落とすケースも多くあります。たとえば、キャンペーンや販促施策に接したにもかかわらず行動に至らなかったという“結果”だけでは、なぜ期待通りに反応しなかったのかは読み取れません。
定性調査を併用しなければ、本当の改善ポイントは見つけにくくなります。
3.特定部門だけで閉じた取り組みになる
マーケティングやUXチームのみでCX改善を試みた結果、営業・CS・プロダクトチームとの整合性が取れず、顧客体験が接点ごとにバラついてしまうパターンです。とくに「オンラインではスムーズなのに、オフラインでは対応が悪い」といった“体験の分断”は、全社的な視点の欠如によるものです。
4.中長期視点を持たない場当たり的な施策
短期的な数値改善ばかりを意識して、「施策を回して終わり」になってしまう企業も見受けられます。たとえば一時的にCVRを上げたとしても、LTVが伸びなければCX施策としての意味は薄いでしょう。継続的にPDCAを回し、改善を積み重ねる視点が欠かせません。
回避策:CX改善を成功に導くためのアプローチ
1.顧客インサイトを深く掘り下げる
データ分析に加えて、ユーザーインタビューや行動観察などを行い、顧客の本音や文脈を理解しましょう。ペルソナ設計やジャーニーマップ作成もこの一環です。感情の動きやフリクションのある場面を可視化することが、質を高めるポイントです。
2.“施策を打つ前”の設計プロセスを重視する
改善施策にすぐ着手するのではなく、「そもそもどこに課題があるのか」「顧客が本当に求めていることは何か」を明確にするプロセスが必要です。情報設計やユーザー行動仮説の立案といった事前準備が、施策の効果を大きく左右します。
3.全社横断のチーム体制を築く
CXは、マーケティング部門だけの責任ではなく、営業・CS・開発・人事などすべての部門に関係するテーマです。顧客接点を持つ各部署が連携し、共通の顧客理解と体験設計のビジョンを持つことで、接点ごとのギャップがなくなり、統一感のあるブランド体験が実現します。
4. 外部パートナーの知見を活用する
自社だけでは気づけない視点やノウハウを補うために、UXリサーチャーやCXコンサルタントといった外部の専門家と連携することも有効です。特に新しい取り組みを導入する際や、既存施策の壁を打破したい場合には、第三者の視点がブレークスルーになります。
まとめ: 顧客体験は“戦略的コミュニケーション設計”で磨かれる
顧客体験の最適化は、単なるUIやデジタル上の操作性を改善することではありません。「どんな文脈で商品・ブランドと出会い、どう記憶されるか」が購買行動に大きく影響します。
だからこそ今、求められているのは、顧客インサイトを起点に、戦略的な販促施策によって最適な体験を設計することです。
とはいえ実際には、「どう設計すれば顧客体験を改善できるのか」「何を出発点に施策を考えるべきか」といった具体的な進め方に悩んでいる企業も少なくありません。
当社では、販促やセールスプロモーションを起点に、購買や来店のきっかけを生み出す体験設計を強みとしています。商品やサービスそのものだけでなく、それに至るまでの体験接点——たとえばキャンペーン、ノベルティ、サンプリング施策など——を含めて設計することで、生活者の記憶に残る体験価値を提供しています。
こうした体験設計に関する課題やご相談にも対応可能です。
外部リソースを活用したデジタル施策もご提案可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
UX再設計の考え方や施策立案のヒントをまとめたホワイトペーパー『セールスプロモーション戦略ガイド』もご用意しています。
読者の「こういうのが知りたかった」を形にした1冊
以下のホワイトペーパーでは、このような内容を体系立ててご紹介しています。
● ニューノーマル時代に対応した3つの戦略視点
(アダプテーション/デジタルとフィジカルの統合/テクノロジー活用)
● キャンペーン・AR・サブスク特典などの体験設計事例
(ファッション×コスメ、AR付きノベルティ、アップサイクル施策など)
● “消費者の心が動く”販促UXをどう組み立てるかのヒント
顧客のペインやニーズから、分析を行いコミュニケーションプランのインサイトを提出し、そのインサイトからどのように効果的なUXを作り上げるのかを掲載しております。
お役立ち資料

ニューノーマル時代のセールスプロモーション戦略ガイド
商品・サービスについてセールスプロモーションを行っているものの、直近の企画がマンネリ化し、効果が低迷しているという方も多いのではないでしょうか。
この原因として、顧客のニーズの多様化があり、この多様化に対応するためには、さまざまなプロモーションの形態・手法を理解することが重要です。
そこで本書では、押さえておくべきセールスプロモーションの形態・手法や最新のトレンドなどをご紹介します。